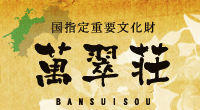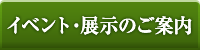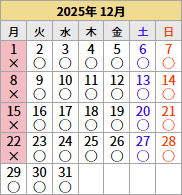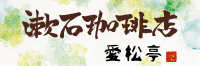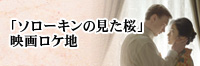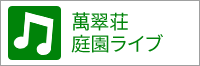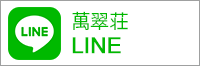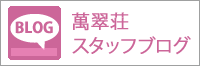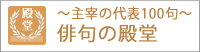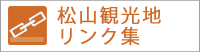萬翠荘 ホームに戻る|俳句の殿堂TOP|~俳句の殿堂~ 黄鳥
黄鳥(コウチョウ)
結社理念

感動を即物表現で最短詩の俳句として表現する。
名利、空論を避け、お互いの個性を尊重し、常に、俳句でなければ表現できない感覚の句を目標に、昨日の俳句に何か をプラスした句を作ることに努力する。
主宰者

小西 領南(コニシ リョウナン)
本名・博孝
大正13年愛媛県生まれ。
昭和17年旧制松山中学卒業。国立興南錬成院(拓南塾)卒業。野村東印度殖産㈱に入社。ジャワ支店・経理部を経て、企業園支配人。ジャワで現地入隊、幹部候補生。終戦。レンバン島に抑留される。昭和21年復員・引揚。関西捺染㈱に入社。昭和50年代表取締役。平成5年退社、現在に至る。
- 俳歴
- 昭和21年
- 「東虹」(芝火)入会
- 昭和23年
- 「天狼」創刊、入会
- 昭和24年
- 「東虹」同人。「俳句ポエム」に同人参加。「東虹賞」受賞。 「炎昼」創刊、入会。
- 昭和28年
- 「炎昼」同人、「炎昼賞」受賞
- 昭和35年
- 「天狼」会友
- 昭和48年
- 「東虹」「俳句ポエム」同人辞退
- 平成6年
- 「天狼」終刊、後継誌「天佰」同人
- 平成8年
- 「炎昼」終刊、「黄鳥」創刊、代表。 俳句協会会員、NPO詩歌句協会理事
『鐵鎖』『冬帽子』『独楽の芯』。他に『現代俳句選集』50句・『歳華悠悠』285句。
連絡先
住所
〒793-0042 愛媛県西条市喜多川390-19
〒793-0042 愛媛県西条市喜多川390-19
主宰の100句
| 1 | 浮きあがるものふえてきし春の沼 |
|---|---|
| 2 | 土筆出る気配の土手となりにけり |
| 3 | 山桜咲けり難所の遍路道 |
| 4 | 春着買ふ妻待つ鏡多きなか |
| 5 | 盆梅展旧き廓の大広間 |
| 6 | 花吹雪今年は横に妻居らず |
| 7 | 位牌の妻見ゆるところに雛飾る |
| 8 | 若布干す砲塁跡の石畳 |
| 9 | 給食に添へし袋の雛あられ |
| 10 | 孔雀ゐて春泥となる檻の中 |
| 11 | 青麦の畝砂浜のなかに消ゆ |
| 12 | 酒倉の大扉を閉める夕桜 |
| 13 | 丸き石あり春の川盛りあがる |
| 14 | 女の抱く犬に舐められ三鬼の忌 |
| 15 | チューリップ開く花弁のはづれるほど |
| 16 | 河口まで来て花筏遡る |
| 17 | 仏具店かがやく春の日が射して |
| 18 | 農具小屋春光返すものありぬ |
| 19 | 滝壺の静まるところ藤映す |
| 20 | 蟹あまた棲みて家運にぬるぎなし |
| 21 | ボート漕ぎ出す推しくれし力継ぎ |
| 22 | 昼に逢ひ花火の傘下にても会ふ |
| 23 | 明け切らぬ道路で氷挽き始む |
| 24 | 瀧のそば瀧とはならぬ水落ちる |
| 25 | 万緑ゆく索道荷札はためきて |
| TOPへ | |
| 26 | 暑き甲板舵の鐵鎖の動きたる |
| 27 | 油槽船灼けて腹より水を吐く |
| 28 | 新緑や畳めり込むピアノの脚 |
| 29 | 草刈機たまに高音出すもの刎ね |
| 30 | 水抜きてプール危険な崖となる |
| 31 | 鰻桶どれがどいつの頭やら |
| 32 | 落蝉の生きゐて指にしがみつく |
| 33 | 形代と流し切れざる癌残る |
| 34 | 採り尽くしたる銅山の青嶺なす |
| 35 | 本堂に鶏上る暑さかな |
| 36 | 万緑の島に神社の千木が出て |
| 37 | 選りて買ふ百円均一蠅叩 |
| 38 | 金魚田の底まで雨のとどきをり |
| 39 | 本殿に昼寝蹠外に向け |
| 40 | 千枚の水田太陽ひとつづつ |
| 41 | プールの水満たして底の線ゆらぐ |
| 42 | 通夜の座の寄せ集めたる扇風機 |
| 43 | 慟哭の洩るる病室梅雨深し |
| 44 | 梅雨探し屍と降りる昇降機 |
| 45 | 炎天に骨壺抱きて躓けり |
| 46 | 船溜まり骨となりなりたる団扇浮く |
| 47 | 紫陽花の群の中より地蔵の顔 |
| 48 | 刺青の男も来たる溝浚へ |
| 49 | 空蝉を吹けばとほくへとびにけり |
| 50 | 蠅叩持ち桟橋に魚売る |
| TOPへ | |
| 51 | あめんぼう跳びて流れに位置保つ |
| 52 | 西日に干す病みたる妻の洗ひ物 |
| 53 | 蟋蟀の身の輝けり闇より来て |
| 54 | 墓石を磨く鶏頭映るまで |
| 55 | 種を採る鶏頭の頭を指で掻き |
| 56 | いなびかり戦乱の世の城となる |
| 57 | 千枚の稲田一枚墓地なりし |
| 58 | 卓上に思索にふける胡桃の脳 |
| 59 | 一触即発たんぽぽの絮の球 |
| 60 | 蜻蛉つるみて琵琶湖中ほどまで来る |
| 61 | 穂絮とぶ岩にも水面にも触れず |
| 62 | 干柿の種も平たくなりゐたる |
| 63 | 葡萄摘み房の重さの手に移る |
| 64 | 耕耘機トラックに乗り疾走す |
| 65 | 盆の寺脱がれて綺羅のハイヒール |
| 66 | 運動会の歓声の島船で過ぐ |
| 67 | 蓮田を出るや泥手で路掴み |
| 68 | 蜩や宿に鞄のもの出しをり |
| 69 | 水たまり乾きて秋の空の消る |
| 70 | 街燈に馴れ夜遊びの石叩 |
| 71 | 鶏頭の頭にのせて軍手干す |
| 72 | 反古の縒りもどる音して夜半の秋 |
| 73 | 地鎮祭雪に浄めの塩を撒く |
| 74 | 冬の石まつすぐ蹴って歩きだす |
| 75 | 蔦枯れて煉瓦の家を金縛り |
| TOPへ | |
| 76 | 雪山の宿天皇の写真古ぶ |
| 77 | 緋袴の巫女参道の雪を掻く |
| 78 | 雪の境内赤き自動車巫女のもの |
| 79 | 真つ先に雪嶺となる神の嶺 |
| 80 | 木槌もて更に平たく干鰈 |
| 81 | 火事場までホースの水のふくれゆく |
| 82 | 寒夜過ぐ大きな駅の明るくて |
| 83 | 寒さ溜りし病廊の突き当り |
| 84 | 水族館鮫が横目でわれを見る |
| 85 | 枯野道石段となり海に入る |
| 86 | 大嚏して自転車のぐらつけり |
| 87 | 枯葦の燃ゆる音して火の見えず |
| 88 | 検札の車掌ゆれつつ大枯野 |
| 89 | 牡丹焚く仏燭をもて火種とし |
| 90 | 天守の窓荒るる海向き雪嶺向き |
| 91 | 病院の前過ぐるとき咳きにけり |
| 92 | 涸河に水幅だけの板の橋 |
| 93 | 芒原踏切ひとつありにけり |
| 94 | 板の道のばして蓮田掘りすすむ |
| 95 | 癌病棟枯野に影を濃くしたり |
| 96 | 夕日受け遠き雪嶺のみ紅し |
| 97 | 澄む点をさぐり当てたる独楽の芯 |
| 98 | 病む妻に並びて買ひし福袋 |
| 99 | 天金の日記帳買ふ快癒して |
| 100 | 言葉交わせず初夢の亡き妻と |