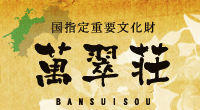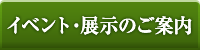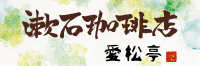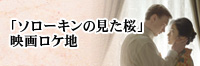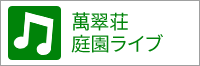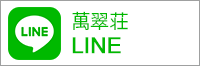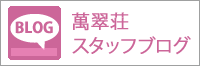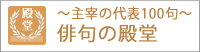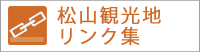萬翠荘 ホームに戻る|俳句の殿堂TOP|~俳句の殿堂~ 嵯峨野俳句会
嵯峨野(サガノ)
結社理念
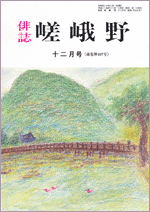
我々は一流一派に偏せず、芭蕉、蕪村に還る志を以ってひろく俳句する心を究め、観照の世界に徹しようとする。有季定型を原則とし、新人もベテランも、ともにその力量のままに句作を楽しむ場をひらきたい。
名誉主宰

阪田 昭風(サカタ ショウフウ)
昭和10年京都に生まれる。会社の転勤先の新潟で「新潟東ロータリークラブ」の俳句会に入会、俳句を始める。昭和58年、村山古郷が夫人の親戚であることを知り、同氏が主宰をしていた俳句結社「嵯峨野」に入会。以後、村沢夏風を生涯の師とし、俳句の方向を定める。
平成3年俳人協会会員。
連絡先
担当
嵯峨野同人会長
中山 仙命
嵯峨野同人会長
中山 仙命
住所
〒225-0001 横浜市青葉区美しが丘西3-28-7
〒225-0001 横浜市青葉区美しが丘西3-28-7
名誉主宰の100句
| 1 | 辛きこと明るく言へり夜の梅 |
|---|---|
| 2 | 春の雪松に降りつつ消えにけり |
| 3 | 苗札を恋名のごとく書いてをり |
| 4 | 幸せを噛みしめてをる目刺かな |
| 5 | 眠りゐし猫を抱きとる雛の前 |
| 6 | 湖に一の鳥居や春の山 |
| 7 | 古郷句碑乙女椿にかしづかれ |
| 8 | 初雲雀赤子は胸をのぼらむと |
| 9 | 石に坐すははを春日のつつみをり |
| 10 | 合格子小さな息を吐きにけり |
| 11 | 少し反る背広の襟や新社員 |
| 12 | 新しき山河展けり春の虹 |
| 13 | 幹に手を置けばやすけし春の雲 |
| 14 | ひたすらに子猫が腹を見せにけり |
| 15 | 天井に棚引く煙二日灸 |
| 16 | 春の海見をり真昼の子の家に |
| 17 | 夕星の光を得たる桜かな |
| 18 | 胎内のごとしさくらのトンネルは |
| 19 | 言訳を深追ひはせず春の昼 |
| 20 | 夕星の空よりさくら吹雪かな |
| 21 | 花散つて雨の修羅場となりにけり |
| 22 | 鉛筆の子の詑状やシクラメン |
| 23 | 旅は良し我が家また佳し花菜漬 |
| 24 | 行く春や繋がれてゆく空ボート |
| 25 | 大川を潮さしのぼる夏隣 |
| TOPへ | |
| 26 | 初夏の港の昼の酒場かな |
| 27 | うすうすと空に富士ある卯波かな |
| 28 | 麦秋やおもかげに立つ阿修羅像 |
| 29 | 生返事責められゐたり夜の薄暑 |
| 30 | 横むくを前に曳かれて競べ馬 |
| 31 | かばかりの余震に目覚め明易し |
| 32 | 栗の花喪服の人が通りけり |
| 33 | 子の釣りし小鯵囲めり一家族 |
| 34 | 空に鳴る風ありにけり初鰹 |
| 35 | 差し伸べる手にきてとまる螢かな |
| 36 | ゆるやかに群れを離るる螢あり |
| 37 | さざ波の光に睦む糸とんぼ |
| 38 | 子の匙を逃げまはりたる苺かな |
| 39 | 少年の心の闇や火取虫 |
| 40 | 旅先の妻と落ち合ふ氷水 |
| 41 | 形代に数へて記す母の齢 |
| 42 | 久にあふ母健やかや走り藷 |
| 43 | 生きもののごとしうごめく背の汗 |
| 44 | 滝の水落つると見しが昇りけり |
| 45 | 一本の麦酒余して下戸家族 |
| 46 | 夏蜜柑指染めて剥く峠かな |
| 47 | はばたきつ蟷螂山の巡行す |
| 48 | 青竹に水たつぷりと鉾回し |
| 49 | 辻回しまはして祇園囃子急 |
| 50 | 南座の灯りてゐたり川床の風 |
| TOPへ | |
| 51 | 朝顔の咲き定まりて力あり |
| 52 | 初秋の光すべるや草の上 |
| 53 | うす煙立つは点火や大文字 |
| 54 | 手を打つて下駄を鳴らして踊の輪 |
| 55 | 稲妻や妻に勤めのこと言はず |
| 56 | 鶏頭の辺り明るき小雨かな |
| 57 | 山の端にふるさとの月大きかり |
| 58 | 草の露朝日隈なくゆきわたり |
| 59 | 露けしや床の窪みし懺悔台 |
| 60 | 灯台のともり夜長の始まれり |
| 61 | 湯上りの母の坐しゐる秋彼岸 |
| 62 | 蟷螂の日ざし曳きずり飛びにけり |
| 63 | こほろぎに指やはらかく噛まれたり |
| 64 | 爽やかに急須の玉露ひらきけり |
| 65 | とまらむとしてとまらざる秋の蝶 |
| 66 | 天心の明るし虫のすだくなり |
| 67 | 玉蜀黍食ぶる子の目のよく動く |
| 68 | ひそやかにして確かなり虫のこゑ |
| 69 | 秋鯖の一句残して逝かれけり |
| 70 | 体操の妻の真顔や小鳥来る |
| 71 | 園丁の箒の先の野菊かな |
| 72 | 残菊にあたらしき花見付けたり |
| 73 | 母在すことの仕合せ秋日和 |
| 74 | 話しゐて妻ふと遠し鰯雲 |
| 75 | 秋風の甕に溢れし山の水 |
| TOPへ | |
| 76 | 冬麗やさざ波しるき阿弥陀堂 |
| 77 | 先生の手がさよならと冬ぬくし |
| 78 | 紅葉散る中ゆく母の美しき |
| 79 | 花八手日当る街を遠く置き |
| 80 | 夏風忌の十一月の不二の山 |
| 81 | 耳に貝あてて潮騒聞いて冬 |
| 82 | ごろごろと河原の石や冬めける |
| 83 | 祓はれて神有月の本殿に |
| 84 | 笑はせて妻を励ます納豆汁 |
| 85 | 枯葦を雀翔ちたる日の光 |
| 86 | 沈む日に一羽たのしとかいつぶり |
| 87 | 水煙に冬満月の瑞みづし |
| 88 | 湯豆腐や俳緑といふ淡きもの |
| 89 | 忘れ物取りに帰りし十二月 |
| 90 | 懐かしき色と思へり枯蓮 |
| 91 | 鴨三羽ほどよき距離に朝の湖 |
| 92 | 母の手に触れて帰りし四温かな |
| 93 | きらめける空淋しめり冬椿 |
| 94 | みな触れて仏足石の氷面鏡 |
| 95 | 大の字に新雪とどめ如意ヶ岳 |
| 96 | 老松に年立つひびきありにけり |
| 97 | たぐひなき日和となりし大旦 |
| 98 | 獅子頭脱げばをみなの匂ひけり |
| 99 | 東山指呼にふるさと松の内 |
| 100 | 客席に紙の雪降る初芝居 |