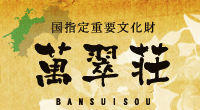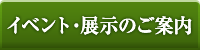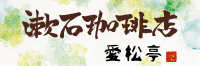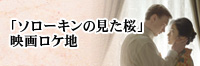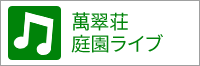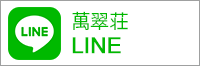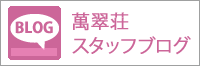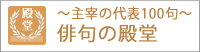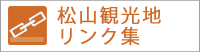萬翠荘 ホームに戻る|俳句の殿堂TOP|~俳句の殿堂~ 星雲
星雲(セイウン)
結社理念
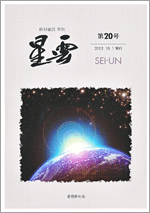
有季定型、表現は清新平明に。人の生と個を尊重し、「もの」と「われ」の「一元」を探る「景情一如」「自然随順」を目指す。
主宰者

鳥井 保和(トリイ ヤスカズ)
昭和27年和歌山県海南市生まれ。
昭和57年山口誓子に師事。同63年「天狼」コロナ賞。平成14年朝日俳句新人賞準賞・同年「俳句界」評論賞。
平成20年「星雲」創刊主宰。
【句集】
『大峯』『吃水』『星天』
俳人協会会員・詩歌句協会理事・朝日新聞和歌山俳壇選者。
連絡先
住所
〒642-0012 和歌山県海南市岡田214-10
〒642-0012 和歌山県海南市岡田214-10
FAX
073-483-4566
073-483-4566
主宰の100句
| 1 | 警策を受け白息をどつと吐く 句集『大峯』より |
|---|---|
| 2 | 卒塔婆を抱きて乗り込む盆列車 |
| 3 | 泣相撲母の胸にてさらに泣く |
| 4 | 天も地も凍て寒柝のよく響く |
| 5 | 墓洗ふ島のいのちの水汲みて |
| 6 | 一切を断つ霧籠めの峯行場 |
| 7 | 大峯に峯雲峯を連ねたる |
| 8 | 峯行者岩跳び岩に抱きつける |
| 9 | 跳び降りてすぐに地を嗅ぐ狩の犬 |
| 10 | 蜑の子の日焼漁師の父よりも |
| 11 | 日本の夜が明く富士の御来迎 |
| 12 | 寒鯉に少しおくれて水動く |
| 13 | 追風に袖拡げゆく流し雛 |
| 14 | 土間に蟹畳には鶏留守の家 |
| 15 | 傘開く水母は海の水中花 |
| 16 | 船腹の大き片陰接岸す |
| 17 | 風倒の稲に重なり案山子伏す |
| 18 | 稲妻に雲の懐中あばかるる |
| 19 | 寒砂丘海の底にも砂の紋 |
| 20 | 初茜一枚となる天と海 |
| 21 | 梅ひらく神慮に叶ふ一枝より |
| 22 | 北帰行天と地の鶴啼き交はす |
| 23 | 吹き抜けし風を追ひゆく花吹雪 |
| 24 | 引く波を力に容れて土用浪 |
| 25 | 一師一代一生誓子曼珠沙華 |
| TOPへ | |
| 26 | 山の端の闇あをあをと冬銀河 |
| 27 | 雪折の木霊の行方深山星 |
| 28 | 校庭の土俵を浄め卒業す |
| 29 | 耕して大地ふくらむうねりかな |
| 30 | 風船の見えて現はる乳母車 |
| 31 | 鳴砂の砂を鳴かせる良夜かな |
| 32 | 北限の一枚の田に案山子立つ |
| 33 | 誓子忌の空のかぎりを星潤む 句集『吃水』より |
| 34 | 白魚は水の色して紛れざる |
| 35 | 一碧の空の芯より那智の瀧 |
| 36 | 深熊野の青嶺が返す青谺 |
| 37 | 命中の鴨の羽毛のおくれ落つ |
| 38 | 焼けてきて餅躍りだす膨れ出す |
| 39 | 湿原の闇ぴしぴしと冬銀河 |
| 40 | 橋の裏まで菜の花の水明り |
| 41 | またひとつ雲の来てゐる袋掛 |
| 42 | 忘れ潮にも夕焼の海の色 |
| 43 | 吃水に昆布躍らせ船戻る |
| 44 | 厠より婆の一喝稲雀 |
| 45 | 木の実独楽横走りして力尽く |
| 46 | 恋螢一期を尽くす火と思ふ |
| 47 | 落日は大魚の目玉鰯雲 |
| 48 | 季語一語一語燈火に親しめり |
| 49 | 活けじめの鯛のいまはのさくらいろ |
| 50 | 一湾の霧押し開く汽笛かな |
| TOPへ | |
| 51 | 風邪に伏し思ふ三鬼の水枕 |
| 52 | 山脈は黒に徹して枯野星 |
| 53 | 春耕のひかりを土にほぐしつつ |
| 54 | 身半分突き出て海女の磯嘆き |
| 55 | 日の温み吐かせ畳める鯉幟 |
| 56 | 黒南風や土まで錆びし造船所 |
| 57 | 水を飲む頸までつけて羽抜鶏 |
| 58 | 鷲掴みして雛舟に雛を載す |
| 59 | 明易の坊摺り足の僧走る |
| 60 | 明易の坊百人の朝餉かな |
| 61 | 燈火親し一推二推敲きけり |
| 62 | 初御空まろし太平洋円ろし |
| 63 | 石鹸玉歪みひと揺れして離る |
| 64 | 海へ石投げては岬を耕せり |
| 65 | 一湾を押しひろげ来る土用波 |
| 66 | 青竹の切口白し夏料理 |
| 67 | 鳶の輪の高きへ絞る深雪晴 |
| 68 | 本山に黒一色の寒の鯉 |
| 69 | 焼藷の二つに割つて湯気二つ |
| 70 | 花嫁に屏風開きの遠雪嶺 |
| 71 | 万蕾に光輪まとふ梅雫 |
| 72 | 鯉跳ねし水輪に春の光かな |
| 73 | 真清水のひかりの底に噴き上ぐる |
| 74 | かたつむり太平洋へ角を振る |
| 75 | 民宿の海の夕日に水を打つ |
| TOPへ | |
| 76 | 神鶏の砂を蹴立てる大暑かな |
| 77 | 屋久島の粒揃ひなる天の川 |
| 78 | 盆の月暈を大きく熊野灘 |
| 79 | 落鮎のいのち躍れる簗の上 |
| 80 | 菊日和蔵に醤の樽を干す |
| 81 | 燈台をすつぽり容れて春の月 |
| 82 | 月涼し熊野へつづく一の宮 |
| 83 | 夕星や近江の宿の洗鯉 |
| 84 | 深熊野に青水無月の雲聳てり |
| 85 | 雲湧いて熊野ふる道草いきれ |
| 86 | 橋脚の片陰となる島一つ |
| 87 | 弓なりの浜夕映えのいわし雲 |
| 88 | 西方に白き雲浮く秋彼岸 |
| 89 | 浮く紅葉沈むもみぢの心字池 |
| 90 | さざ波のごと粉雪の地を這へり |
| 91 | 隠沼に亀泳ぎゐる山桜 |
| 92 | 衝立は洛中洛外花見茶屋 |
| 93 | 滴りのみどりに苔の熊野道 |
| 94 | 石一つ置くだけの墓苔の花 |
| 95 | 一山の天蓋となる雲の峰 |
| 96 | 合歓咲いて瀞の碧さの底知れず |
| 97 | 文机がひとつ遺影の夏座敷 |
| 98 | 獅子岩の獅子の咆哮いなびかり |
| 99 | 深熊野の瀞のさやけし夕月夜 |
| 100 | 散紅葉載せて羅漢の笑みたまふ |