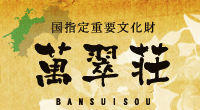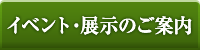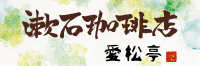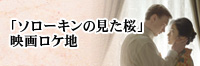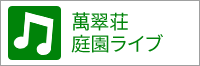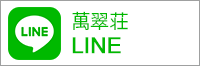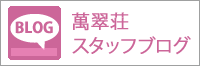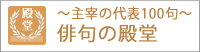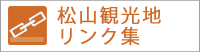萬翠荘 ホームに戻る|俳句の殿堂TOP|~俳句の殿堂~ 城
城(シロ)
結社理念

昭和3年11月1日ホトトギス同人山本村家を雑詠選者として松江市で創刊。以来個人誌とせず、誌友共有の公器として運営する。
平成25年1月号で968号。
主宰者

佐藤 夫雨子(サトウ フウシ)
(本名)密法 (出身)旧朝鮮慶尚南道密陽
昭和3年4月25日生まれ。
昭和20年引揚、米子市役場40年・福祉法人14年勤務。
昭和30年句作始め、現在「城」主幹。俳人協会評議員(県支部長)・伝統俳句協会幹事。
【参加誌】
『ひいらぎ』『夏炉』『かつらぎ』『ホトトギス』
【句集】『山開』
連絡先
住所
〒683-0004 鳥取県米子市上福原5-13-78
〒683-0004 鳥取県米子市上福原5-13-78
FAX
0859-22-5644
0859-22-5644
主宰の100句
| 1 | 麦の芽のそよぐけはひや濤の音 |
|---|---|
| 2 | 冬湖に壺網を張るのみの漁 |
| 3 | 大雪崩天狗倒しと云はれけり |
| 4 | 松の枝の雪と地の雪繋がれる |
| 5 | 納棺や手なれし杖を足袋を入れ |
| 6 | 寝返りをせし子に蹴られ明易し |
| 7 | げんげ田に水ありしとは知らざりし |
| 8 | バーの灯に防犯の灯に雪荒ぶ |
| 9 | 波蹴って日本海の鴨を撃つ |
| 10 | 楮搗く三つの杵のよく揃ひ |
| 11 | 砂が眼に入りて休むや松露掻 |
| 12 | 松露掌にあふれ日本海晴るる |
| 13 | 水口に石を祀りて山葵沢 |
| 14 | 出漁の網積む唄や月見草 |
| 15 | 網引くやこうぼふ麦の実を飛ばす |
| 16 | 砂つぶて浜昼顔の上を飛ぶ |
| 17 | 伯楽を止めてこの方鮎の宿 |
| 18 | しるべにはあらず紅葉の枝が折れ |
| 19 | 頭越しおでんの皿の渡さるる |
| 20 | 鴨の銃ありし干拓事務所かな |
| 21 | 白牡丹撃たれしごとく崩れけり |
| 22 | 水撒のホース向ければ月涼し |
| 23 | とんどの火ちぎれ日本海に飛ぶ |
| 24 | ドラム缶山と積まれて雪の果 |
| 25 | 水あれば木あれば雪解いそぐなり |
| TOPへ | |
| 26 | 鯵売の車洋傘さして引く |
| 27 | 店の灯にあまたの色の種袋 |
| 28 | ソ連船見えて休みぬ防風摘み |
| 29 | 藍甕にほかりと梅雨の薄日かな |
| 30 | 隠岐見えてゐて高々と烏賊を干す |
| 31 | 骨折とひとことスノーボード曵く |
| 32 | 師をはさみ女流作家やビアホール |
| 33 | 真ん前に崖が崩れて鮎の宿 |
| 34 | 秋天に投げて濯ぎの衣を干す |
| 35 | 台風のさなか電話は父の訃を |
| 36 | スキー隊樏隊ら救助行 |
| 37 | 青芝に膝まくらして恥らはず |
| 38 | 炎天下十万人のごみを焼く |
| 39 | 都市のごみ焼く日々蜻蛉とびかはす |
| 40 | 八雲立つ風土記の丘は稲架襖 |
| 41 | 奥日野の沢蟹のすきとほりたる |
| 42 | 絮の尽きたる枯芒直立す |
| 43 | 立春の双曲線を画く雨 |
| 44 | 山陰の上海といふ花篝 |
| 45 | 千と云ひ万と云ふ炬火山開 |
| 46 | 水着派手美しき娘にあらずとも |
| 47 | 潮の引くままに寄居虫みな動く |
| 48 | 大山の雲払ひけり威銃 |
| 49 | 花芒解くべく弓を張りにけり |
| 50 | サーカスのピエロでありし昼寝人 |
| TOPへ | |
| 51 | 和布刈祢宜しばしば袖に風はらむ |
| 52 | 真先に蟹はづさるる地曳網 |
| 53 | 稲妻のゆたかな夜見の国に住む |
| 54 | 隠岐からのそよそよ風や菜を間引く |
| 55 | 芋鳴いてをるかと思う芋水車 |
| 56 | 烏瓜ひとつ揺るるはなぜならん |
| 57 | 通りみちのこして波止の干鰯 |
| 58 | 流鏑馬を待ちをる馬や花の幹 |
| 59 | 一つづつキャンプの火屑木をのぼる |
| 60 | 天草を下さねば舟揚らざる |
| 61 | 絞られて染糸泣けり寒灯下 |
| 62 | 鯉の水戸毎に花の城下町 |
| 63 | 手のとどく北斗七星山開 |
| 64 | 郭公や伽羅木地帯晴れ渡り |
| 65 | 大山を妹山とせり雲の峰 |
| 66 | 腕白の礫に案山子ひるまざる |
| 67 | 吾が積みし石を崩すや天高し |
| 68 | 自転車を押しくだされし神渡し |
| 69 | おでん屋に漢方薬師格勤な |
| 70 | 隠岐の上に八重の棚雲海苔を掻く |
| 71 | 吾が捨てし村に戻りぬ農具市 |
| 72 | 朝酒に酔へる翁や農具市 |
| 73 | 秣桶叩いてみせて農具市 |
| 74 | 五輪墓二百三百山桜 |
| 75 | フレームに応接セットまで置きぬ |
| TOPへ | |
| 76 | 霧少し動いてをりぬ御来迎 |
| 77 | 人麻呂のゆかりの海を泳ぎけり |
| 78 | 氷室の扉天の岩戸のごと開く |
| 79 | 後醍醐の船出の磯の海苔を採る |
| 80 | スキーヤー雲よりこぼれきたりけり |
| 81 | 花の僧尼子毛利に荷担せず |
| 82 | 石垣を積む島畑の馬鈴薯の花 |
| 83 | 鰡かなし嫁泣湾に養はれ |
| 84 | 扇風機こちら向かざる法事かな |
| 85 | スケーター大円盤を画きけり |
| 86 | 鉈の刃のみなこちら向き農具市 |
| 87 | 一挙手に一投足に目高散る |
| 88 | 一とかかへ買ふ松明や山開 |
| 89 | 大山の落石絶えずほととぎす |
| 90 | 炎天下青といふ色なき砂丘 |
| 91 | ダム工事中は人殖え盆踊 |
| 92 | 若水を天の真名井に掬びけり |
| 93 | 白鳥の来てをらぬとき只の村 |
| 94 | 夕蛙ベビーホテルは哀しき名 |
| 95 | 古の一揆の村の農具市 |
| 96 | 糠雨に濡るる外なし農具市 |
| 97 | 顔の渋紙色や農具市 |
| 98 | 後醍醐の御舟出の町農具市 |
| 99 | 万緑に三百年の絣織る |
| 100 | コールテンには付かざりし草虱 |